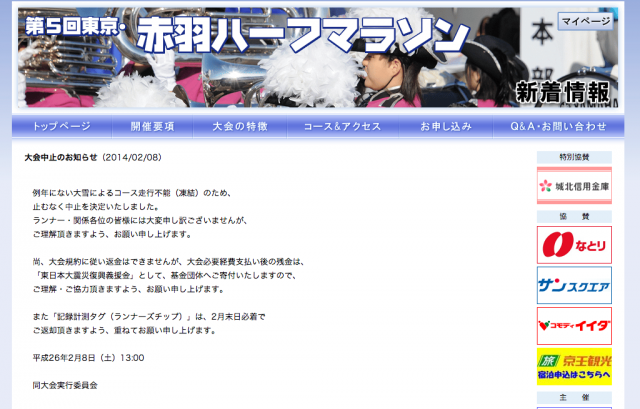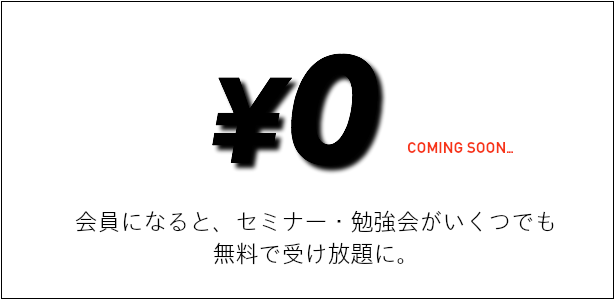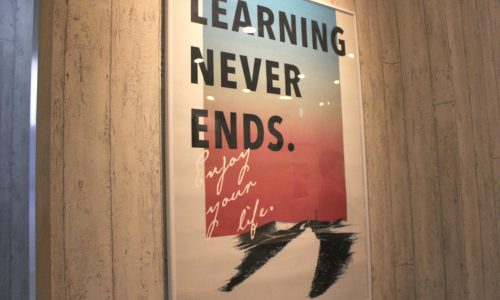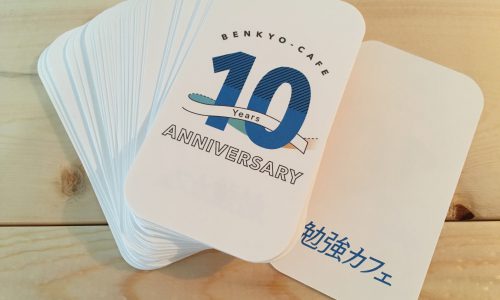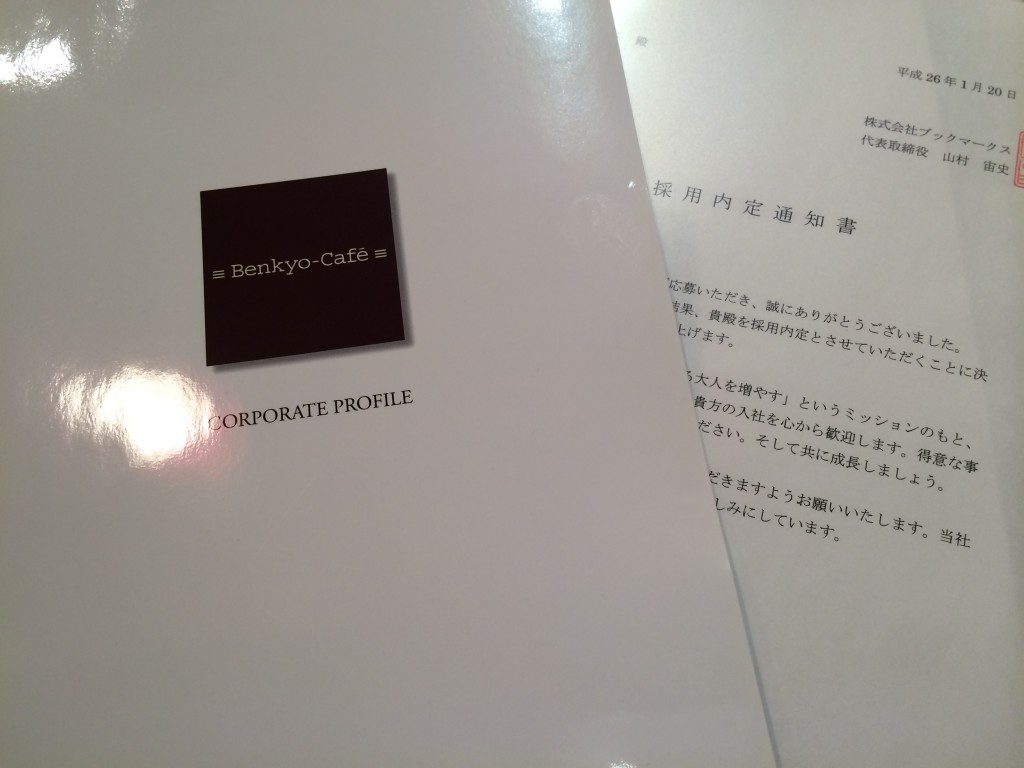
来月から1名、そして4月からもう1名、それぞれ女性社員が入社することになり、先日「採用内定式」なるものを初めてやりました。一人は新卒です。08年に創業したので6年目にして初の新卒社員。自分の作った会社にも新卒が入るかと思うと感慨深いです。よく言われることですが、新卒で入社する会社の影響を(良い意味でも悪い意味でも)大きく受けるのが新卒の会社だと思います。逆に中途で入社してくる社員は、本人が新卒で入社した会社の仕事の仕方や考え方の影響を少なからず受けています。
この春入社してくる彼女が今後どういう人生を歩むにしても、数ある会社の中から当社を選んでくれた以上、せめて理念を追求する集団で仕事をしたことを後々誇りに思ってもらえるような会社にしたいと思います。
まだやってもいないのに「これをこれからやる!」的な投稿ってイケてないし格好悪いと思うので何も言わないでいましたが、会社の戦力の底上げとさらなる理念共有を図るために何をすればよいのか、この年末年始いろいろ考えました。そしてそれを開始しました。何かを変えるためには自分が変われなければいけない。
まずは、【職位と雇用形態の明確な区別】です。「マネジャー=正社員」。世間一般では当たり前といえば当たり前。僕もそう思っていました。各店には社員がマネジャーとして必要だと。しかしそれは本当だろうか。必ずしもその限りではないと思えるようになりました。マネジャーは職位であり、正社員である必要はない。アルバイトは下で、社員が上といった常識を壊して組織づくりをしようと決めました。そして同時に、正社員や非正規社員(アルバイト)以外の雇用形態はないものか検討しました。そこで取り入れてみたのが、昨年政府の雇用制度改革のひとつとして盛り込まれた、限定正社員(ジョブ型正社員)の導入です。
*限定正社員については下記の記事が分かりやすくまとまっています。
時論公論 「限定正社員は誰のため」 | 時論公論 | 解説委員室:NHK
サービス業はどうしても勤務時間が不安定で休日も不定休になりがちです。私も外食店長時代に土日に休んだ記憶が殆どありません。他の人が休む時に働くのがサービス業の現場で働く宿命なので仕方のない面はあるのですが、負担はやはり大きいですし、家庭を持つ身だと一層ですよね。幸い勉強カフェでは土日も休める機会もそれなりにありますが、そもそも、ひとつの会社でその仕事だけをするという労働観そのものが今後一層変わっていくと思います。実際、副業や兼業をしている会社員も増えています。既婚者であれば家族との時間を優先するために労働時間を抑えたい人もいるでしょう。働きながらも他に学びたいこともあるでしょう。
つまり、働き方が多様化している中で、それに応じて、勤務時間を残業のない実働8時間に抑え、異動もなく勤務地も本人の希望に則したものに、その分給与や報酬は正社員より少ない、としたのが弊社で言う限定正社員となります。(他にもありますが大まかにはこのような形です)今回、新しく入る女性社員は2名とも限定正社員での契約です。当然、正社員だから上で、限定正社員だから下、ではありません。どちらも同じく大事な仲間であり、同列です。限定正社員だからマネジャーになれないわけでもありません。違うのはあくまで雇用形態の違いであって、あくまでマネジャーになれるかどうかは、能力次第です。
そのうえで、【アルバイトスタッフ主体の店舗運営体制】を敷いていきます。別に人件費の削減が目的ではありません。先行実施店舗では実際それほど変わっていません。ここで取り上げたいのは、スターバックスのスタッフ(パートナーと呼ぶそうです)やオリエンタルランドのスタッフ(キャスト)です。どちらの会社もアルバイトスタッフが運営の主体となっており、そして、にも関わらずサービスレベルがとても高いと各方面で評判の両社。本当に有難いことですが、当社運営の勉強カフェにも、とても主体的で気の利くスタッフが大勢集まっています。彼らにとってさらに能力を発揮して貰える仕組みと環境の整備を進めていきます。
他にもアルバイトスタッフへの店舗数字の開示(全社員への業績数字の開示は既に行っています)、これまで当たり前のように社員だけで行ってきた全体会議へもアルバイトスタッフが参加できるようにしました。と同時に、理念のさらなる共有を図るべく週1回、僕からアルバイトスタッフを含めた全員に対してメッセージを配信し始めました。これは僕のルーティンとして頑張って続けます。さらに、僕の午前中の時間を開放し、社員/アルバイトスタッフ問わず来れる人が集まり、相談したりディスカッションしたり企画立てたりできるようにしました。また専門的な職務のスキル獲得を支援・評価する「マイスター制度」も試験運用中です。
僕自身の思考がここに辿り着くまでに相当の時間がかかりました。人に関わる判断ミスも何度もしました。ほんとうに難しいです。昨秋にも焦りからやや大きな授業料を払ってしまいました。でもどの経験も必要なことだったのかなと思います。
今回始まることはどれもひとつひとつは小さなことですが、これが1年後には大きな実になることを期待しています。

考えてみれば、今回始めたことは、昨年開始した勉強カフェアライアンスと同じことだな、とも思います。加盟希望の方へのメッセージのところに書いてあるとおり、アライアンス制度創設の発端は、勉強カフェの出店を全部自前でやるのを止めるという決断を下したこと、でした。今回始めたのは、自分のやっていた仕事のうち、他と比較して自分のあまり関心の高くない点や弱い点は、それをやりたい人に権限移譲するということ。
「社長は会社業務から完全に外れて、1ヶ月くらい海外とかどっか行って、新しいアイディア見つけて戻ってくるくらいがちょうど良い」と昔何かで読んだことがありますが、そうかもしれないですねぇ。まだまだその金銭的余裕と勇気はないですが^^;
これまでたくさんの本を読んで真似できるものはないか調べてきました。たくさんのやり方や制度があるわけですが社風に合うものとそうでないものもあります。現時点で参考にするのを決めたのはサイバーエージェントであり、また、アルバイトスタッフが主体的に楽しく働く仕組みを有するスターバックスでありオリエンタルランドです。
仕組みや新しいサービス等はそれ自体に参入障壁は無いので、思いついても簡単に真似されてしまいがちですが、理念の浸透度合いとスタッフの主体性といったのはそうはいかないんですよね。やるからには、自習室業界(?)におけるスタバやオリエンタルランドを目指し、差別化を一層進めていきます。「学ぶ大人が夢を叶える場所ー勉強カフェ」ってな感じで。
スポンサーリンク